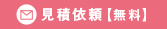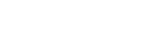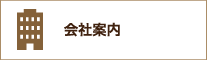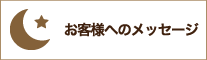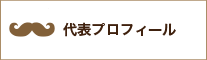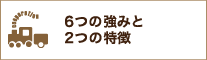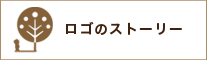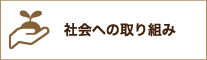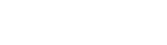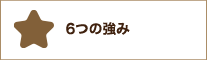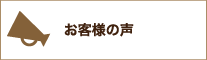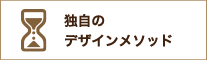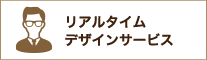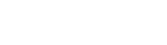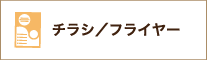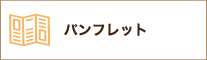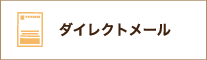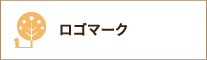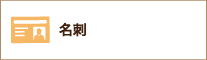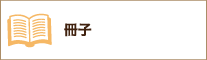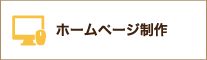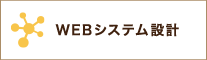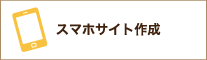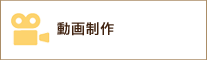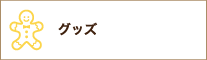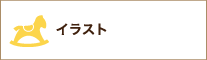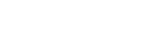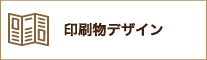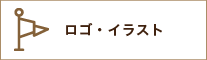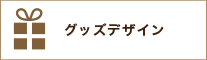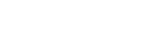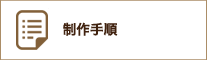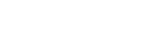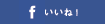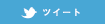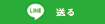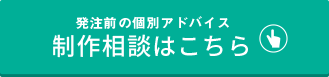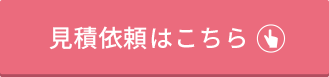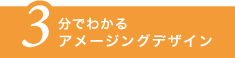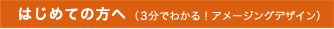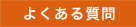TOPICS
デザイナーに「おまかせ」してうまくいくケース・失敗するケース
「デザインのことはよく分からないから、とりあえずデザイナーに任せよう」
そう考えたことがある方は多いのではないでしょうか。
実際、プロに任せるのは賢い選択です。しかし、すべてを『おまかせ』にした結果、「イメージと違った」「効果につながらなかった」と後悔するケースも少なくありません。
では、デザイナーにおまかせするとうまくいくケースと、逆に失敗してしまうケースの違いはどこにあるのでしょうか。
今回は、その境界線を明らかにしながら、成果を出すための依頼の仕方を解説していきます。

目次
おまかせが成功するのは「ゴールが明確なとき」
デザイナーに任せて成功するのは、依頼主が「何を達成したいのか」を明確に伝えているときです。
例えば、「新規顧客を増やすためのチラシを作りたい」「採用サイトで応募者の数を増やしたい」といったゴールが具体的であれば、デザイナーはその目的に合った表現やレイアウトを提案できます。
依頼主が細かいデザイン要素まで指定しなくても、ゴールさえ明確ならデザイナーは専門的な判断で成果に近づけるデザインを形にできます。
おまかせで失敗するのは「目的が曖昧なとき」
逆に、依頼が失敗につながるのは「目的がはっきりしていない」ケースです。
「とりあえず見栄えを良くしたい」「なんとなくオシャレにしたい」といった依頼では、完成したデザインが成果につながる保証はありません。
目的が曖昧なままでは、デザイナーも方向性を定めづらく、結果として依頼主の期待とかけ離れた仕上がりになることが多いのです。
「見た目」だけ任せるのは危険
おまかせが失敗しやすいもうひとつの要因は、『見た目だけを重視する依頼』です。
デザインは単なる装飾ではなく、情報を整理し、ターゲットに伝わるための仕組みです。色や形だけをデザイナーに委ねても、戦略的な観点が抜け落ちてしまえば成果には直結しません。
「なぜこの色なのか」「なぜこのレイアウトなのか」といった裏付けを持った提案を受けられるように、依頼主側も目的や顧客像を共有することが不可欠です。
成功する「おまかせ」の依頼方法
おまかせを成功させるためには、以下のような姿勢が役立ちます。
・目的やターゲットを明確に伝える
・競合や参考にしたい事例を共有する
・「成果が出るための判断はデザイナーに委ねる」と伝える
こうした情報があることで、デザイナーは依頼主の期待に応えやすくなり、プロとしての力を最大限に発揮できます。
『おまかせする部分』と『共有すべき部分』を分けて考えることが、成功の鍵となります。
フィードバックは「違和感」を伝えることが大切
おまかせしたとしても、制作の途中で「何か違う」と感じることはあります。
そのときに大切なのは、『違和感を率直に伝えること』です。
ただし「なんか違う」だけではデザイナーは修正の方向性を見極めにくくなります。「もっと親しみやすさを出したい」「高級感を強調したい」といった具体的な言葉に変えるだけで、修正がスムーズに進みます。
納品後の運用で差が出る
おまかせで成果が出るかどうかは、実は納品後にも左右されます。
特にホームページやLPの場合は、公開後の反応を見て改善を繰り返すことが重要です。デザイナーにおまかせした初期デザインが完璧でなくても、データを基に改善することで結果を伸ばせます。
その意味で、運用を一緒に考えられるデザイン会社やデザイナーに依頼することが、長期的な成功につながります。
まとめ
デザイナーに「おまかせ」すること自体は決して悪いことではありません。むしろ、目的やターゲットが明確であれば、プロの判断に委ねることで成果を高められます。
しかし、目的が曖昧なまま「オシャレにしてほしい」と依頼するだけでは、期待外れの結果になるリスクが高まります。
おまかせで成功するには、『依頼主が伝えるべき情報』と『デザイナーに委ねる判断』を整理して臨むことが欠かせません。
成果を生むデザインは、依頼主とデザイナーの協働によって形づくられます。おまかせする部分と関わる部分をバランスよく見極めることで、納得のいく結果を得られるはずです。

私たちアメージングデザインでは、戦略設計から参加し、企業やサービスの強みを「伝わるカタチ」にするサポートを行っています。
見た目だけでなく、「伝わるための仕組み」としてのデザインが必要な方は、ぜひご相談ください。
「結果に直結するデザイン」を、プロジェクトの初期から一緒に考えてみませんか?