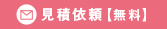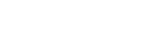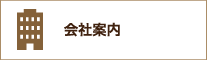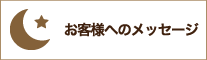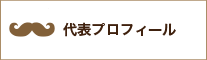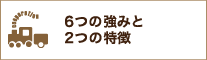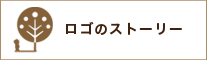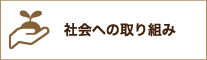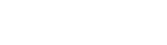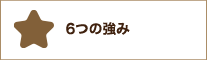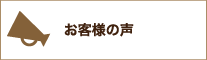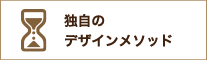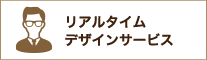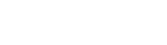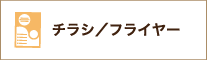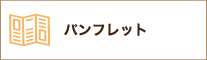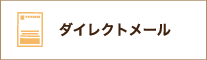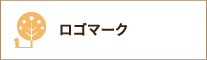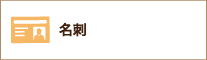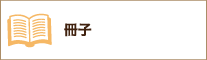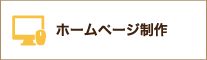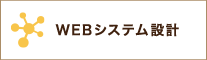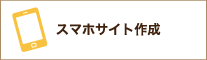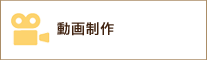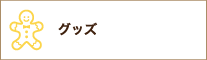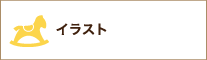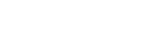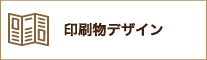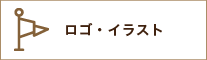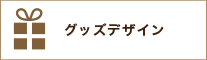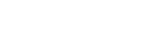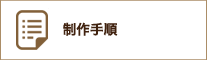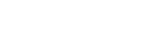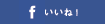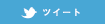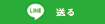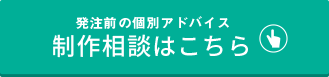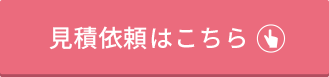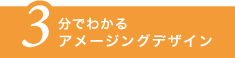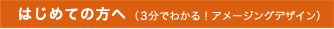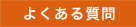TOPICS
更新しないホームページが信頼を失う理由と改善策
「ホームページを作ったのに、問い合わせが増えない」
「何年も更新していないけれど、まだ使えるはずだ」
そう考えている企業やお店は少なくありません。
しかし実際には『更新されていないホームページ』ほど、ユーザーからの信頼を失いやすいものです。
デザインや情報が古いままのサイトは、来訪者に「この会社は本当に活動しているのか?」と疑念を抱かせてしまいます。
信頼が揺らげば、せっかくのサービスや商品も検討の土台にすら上がらない可能性があるのです。
この記事では「なぜ更新されないホームページが信頼を失うのか」そして「改善のためにできること」を、具体的な視点からお伝えします。

目次
情報が古いことによる不安感
ホームページは企業やお店の『顔』ともいえる存在です。
ところが、掲載している情報が何年も前のまま放置されていると、ユーザーに「もう活動していないのでは?」と不安を与えます。
特に以下のようなケースは信頼を損ないやすい例です。
- 最新のニュース欄が数年前の日付で止まっている
- 掲載されているスタッフや料金が現状と異なる
- イベント情報が過去のまま残っている
こうした小さな違和感が積み重なることで、ユーザーは「ここに依頼して大丈夫だろうか」と感じ、他社サイトへ流れてしまいます。
検索エンジン評価の低下
更新されていないホームページは、SEOの観点からも不利になります。
Googleをはじめとした検索エンジンは「最新で有益な情報を提供しているサイト」を評価します。
逆に言えば、情報が更新されず変化がないサイトは「価値が低い」とみなされやすく、検索順位が下がってしまうのです。
順位が下がれば訪問者が減り、結果的に問い合わせのチャンスも逃してしまいます。
つまり、更新を怠ることは「ユーザーの信頼」と「検索からの集客」の両方を失うことにつながります。
デザインの古さが与える印象
デザインも信頼性を左右する大きな要素です。
数年前はスタイリッシュに見えたデザインでも、現在の基準では「古臭い」「操作しづらい」と感じられることがあります。
例えば、スマートフォン表示に対応していないサイトは、今の時代では大きなマイナスポイントです。
ユーザーはストレスを感じ、すぐに離脱してしまうでしょう。
情報が正しくても、見た目や操作感が古ければ「管理されていない印象」を与えてしまいます。
更新しないことで失うビジネスチャンス
更新されていないホームページは、集客やブランディングの面で大きな損失を生みます。
ユーザーが求めているのは「今、この瞬間に役立つ情報」だからです。
更新されていないサイトでは、以下のような機会を逃してしまいます。
- 新商品やサービスをアピールするタイミング
- イベントやキャンペーンで来店を促す機会
- お客様の声や実績を活用した信頼構築
ホームページは「24時間働く営業マン」です。
その営業マンが古い資料しか持っていなければ、成果が出ないのは当然といえます。
改善のための基本的なアクション
では、更新されないホームページを改善するために、どのような取り組みが必要なのでしょうか。ポイントを整理してみましょう。
- まずは基本情報(会社概要・営業時間・料金など)を最新に保つ
- 定期的にニュースやお知らせを更新し、活動の継続を示す
- 実績や事例を追加し、信頼性を高める
- 写真やデザインを見直し、現代的で見やすいサイトにする
- スマートフォン表示を最適化し、利便性を確保する
重要なのは「一度に大掛かりなリニューアルをしなくても良い」という点です。
まずは小さな改善を積み重ねることで、信頼を取り戻すことができます。
社内で更新を続ける仕組みを作る
改善をしても「また放置してしまう」のでは意味がありません。
そのために必要なのは『更新を続ける仕組み』です。
例えば以下の工夫が効果的です。
- 月に一度、担当者がチェックするルールを作る
- 社内で誰でも更新できるCMS(WordPressなど)を導入する
- 制作会社に更新代行を依頼し、継続的にサポートを受ける
仕組みを作って「更新を日常化」することで、常に新鮮な情報を発信でき、信頼を維持できます。
まとめ
更新されないホームページは、ユーザーの信頼を失い、検索からの集客も弱まり、ビジネスチャンスを逃してしまいます。
逆に、継続的に更新されているサイトは「今も活動している安心感」「情報の新鮮さ」を伝えられ、顧客からの信頼を獲得できます。
小さな更新からでも構いません。
継続的に情報を整え、見た目や使いやすさも見直すことで、ホームページは再び成果を生み出す資産となります。

私たちアメージングデザインでは、戦略設計から参加し、企業やサービスの強みを「伝わるカタチ」にするサポートを行っています。
見た目だけでなく、「伝わるための仕組み」としてのデザインが必要な方は、ぜひご相談ください。
「結果に直結するデザイン」を、プロジェクトの初期から一緒に考えてみませんか?