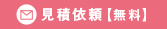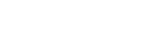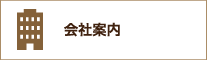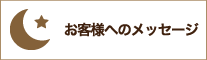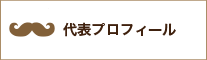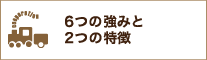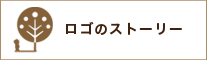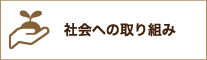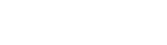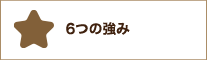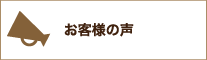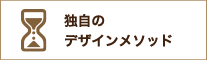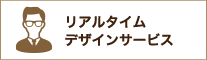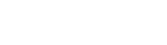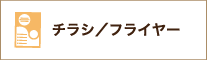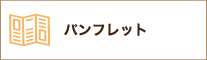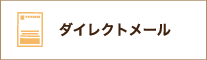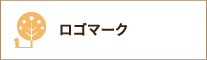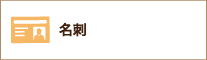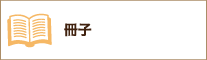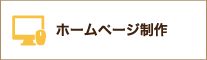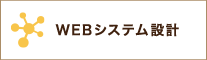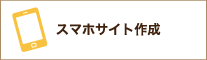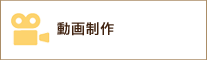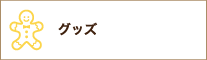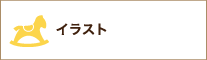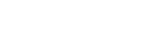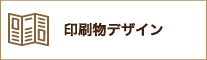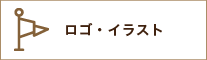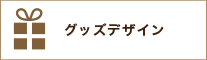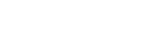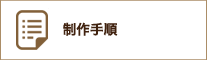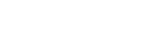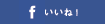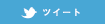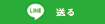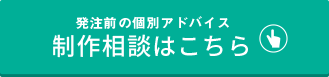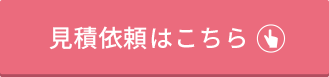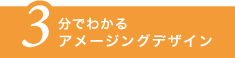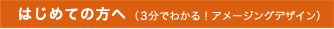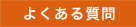TOPICS
社内のデザイン教育が必要な理由とその始め方
「デザインは専門家に任せればいい」「社内のメンバーがデザインを理解していなくても問題ない」
そう思っている経営者や担当者の方は少なくありません。
確かに、専門的なデザインスキルを全員が持つ必要はありません。しかし、社内でデザインに対する理解が不足していると、外部に依頼した際に意図が伝わらなかったり、制作物のクオリティがバラついたりといった問題が生じやすくなります。
経営やマーケティングの現場で成果を上げるためには、社員一人ひとりがデザインを「単なる装飾」ではなく「価値を伝える手段」として理解することが欠かせません。
今回はデザイン会社の視点から、なぜ社内のデザイン教育が必要なのか、そしてどのように始めるべきかを解説します。

デザイン教育が必要とされる背景
デジタル化が進み、顧客との接点は多様化しています。
ホームページ、SNS、チラシ、営業資料など、あらゆるシーンで「視覚的な表現」が企業の印象を決定づけています。
そのため、社内にデザインに関する理解が不足していると以下のような課題が生じます。
・自社の資料や発信に一貫性がなく、信頼感を損ねる
・外部デザイナーとのやりとりで齟齬が多く、成果物が想定とズレる
・マーケティング戦略とデザイン表現が噛み合わない
こうした課題は、単にデザイン担当者だけの問題ではなく、経営や営業の成果全体に直結します。だからこそ、社内全体でデザインの基本理解を深めることが必要なのです。
デザイン教育がもたらすメリット
社内にデザイン教育を導入することで、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。
・ブランドイメージの一貫性が保たれる
・外部デザイン会社とのコミュニケーションがスムーズになる
・企画やマーケティングの段階から「伝わる表現」を意識できる
・社内制作物のクオリティが底上げされる
特に重要なのは「社内の意思決定スピードが早くなる」点です。
デザインに対する基礎知識があれば、修正依頼や判断基準が明確になり、外部委託のコスト削減にもつながります。
社員全員がデザイナーになる必要はない
ここで誤解してはいけないのは「社員全員に専門的なデザインスキルを身につけさせる必要はない」ということです。
必要なのは、あくまで「デザインの役割や基本的な原則を理解すること」です。
例えば、以下のような視点を社員が理解しているだけでも大きな違いが生まれます。
・情報を見やすく整理することの重要性
・色やフォントが与える心理的な印象
・顧客目線でのわかりやすさを重視すること
このような基本的なデザインリテラシーを持つことで、社内の企画や資料が格段に伝わりやすくなり、外部デザイナーとの連携もスムーズになります。
デザイン教育を始めるステップ
では、実際に社内でデザイン教育を導入するにはどうすればよいのでしょうか。おすすめのステップを紹介します。
・まずは経営層が「デザインを経営資源とする」方針を示す
・社員全員が参加できる基礎研修を実施する
・実務に直結するテーマ(資料作成、SNS投稿など)を題材に学ぶ
・外部のデザイン会社や専門家を招いてレクチャーを受ける
・学んだ内容を実際の業務に取り入れ、定期的に振り返る
大切なのは「学びっぱなしにしない」ことです。
実際の業務に落とし込む仕組みをつくることで、教育効果が社内に定着します。
外部デザイン会社を活用するメリット
社内で独自に教育を進めるのは難しい場合、外部のデザイン会社をパートナーとして活用する方法もあります。
実際のプロジェクトを進めながら「なぜこのデザインが効果的なのか」を解説することで、実践的な学びが得られます。
さらに、外部の視点が加わることで、社内では気づきにくい課題や改善点を発見できるのも大きなメリットです。
まとめ
社内のデザイン教育は、単なるスキル向上ではなく「企業全体の成果を底上げする仕組み」です。
全員が専門家になる必要はありませんが、社員がデザインの基本理解を持つことで、外部パートナーとの連携がスムーズになり、ブランドの一貫性や成果に直結します。
「社内の誰もがデザインを理解できる組織」をつくることは、これからの企業にとって大きな競争優位性となるでしょう。

私たちアメージングデザインでは、戦略設計から関わり、デザイン制作だけでなく「社内でデザインを活かすための仕組みづくり」もサポートしています。
単なる制作依頼ではなく、社員と共に「伝わるデザイン」を育てたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。
「結果に直結するデザイン」を、教育と仕組みづくりの両面から一緒に考えてみませんか?