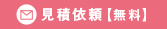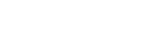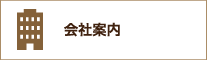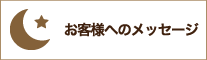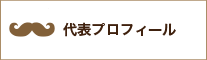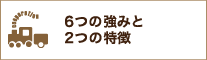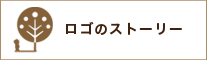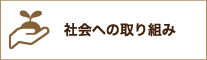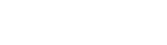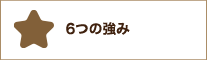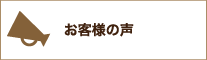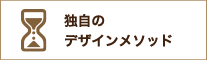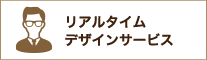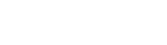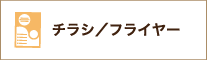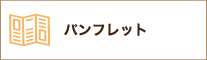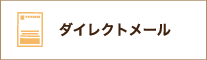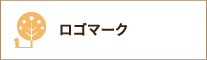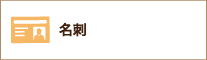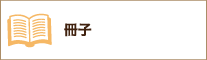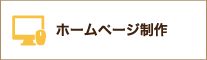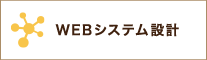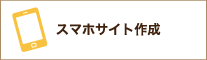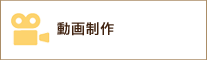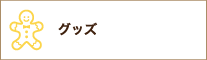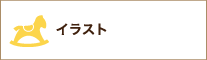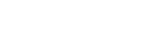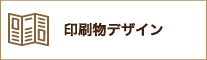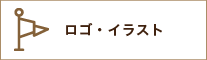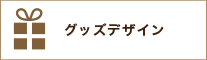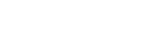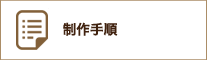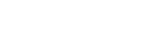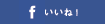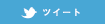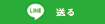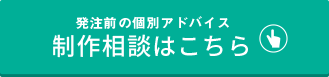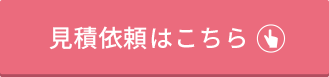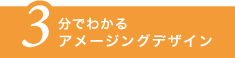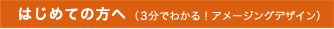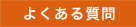TOPICS
経営視点で見る、デザイン投資の費用対効果とは
「デザインにお金をかけるのは無駄ではないか」「売上に直結しないのに、なぜ高い費用を払う必要があるのか」
そんな疑問を持つ経営者の方は少なくありません。
確かに、デザインは広告のように即効性のある施策とは違い、効果を数値で測りにくい側面があります。
しかし、経営の視点から長期的に見れば、デザインへの投資は「コスト」ではなく「資産」になります。
本記事では、デザイン会社の立場から「デザイン投資の費用対効果」を経営の視点で整理し、なぜ成果につながるのかを解説します。
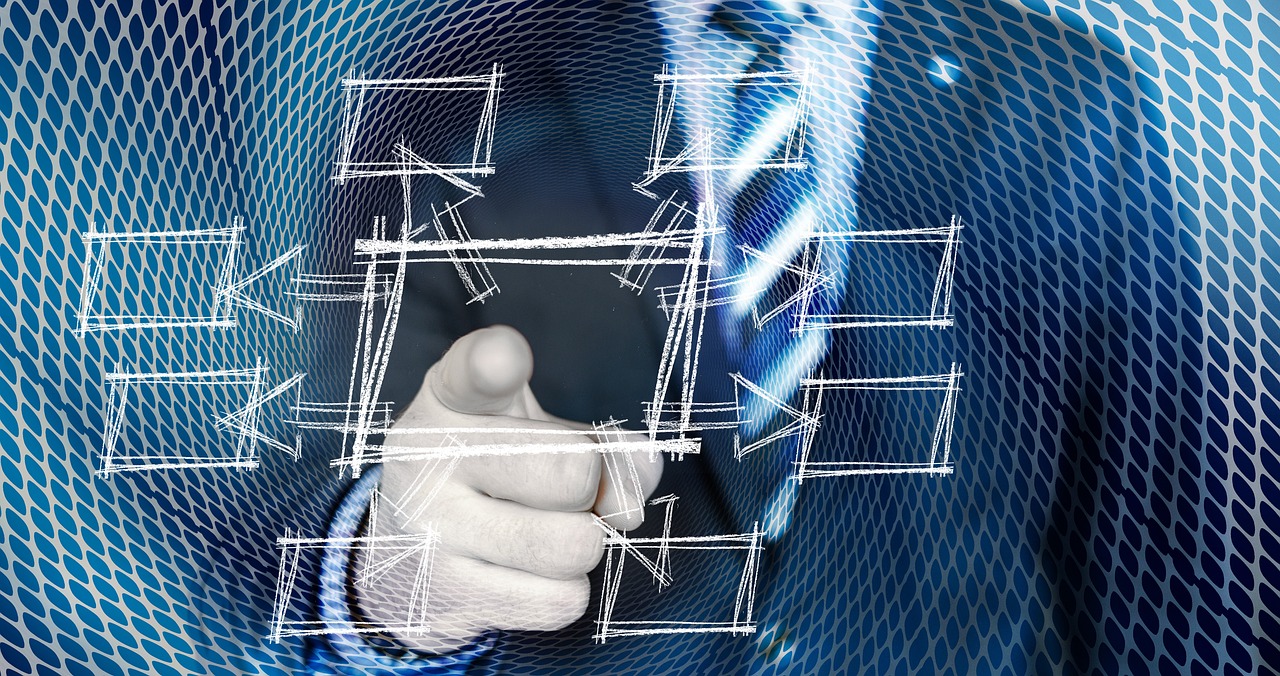
目次
デザインは単なる装飾ではなく「経営資源」
まず理解すべきは、デザインは「見た目を整えるためのもの」ではなく、企業活動を支える重要な経営資源であるという点です。
ブランディング・商品開発・広告・営業資料など、あらゆる接点でデザインは企業の印象を形づくります。
もしデザインが不十分であれば、せっかくの良い商品やサービスも顧客に正しく伝わらず、機会損失を生むことになります。
逆に、戦略に沿ったデザインは「企業の強みをわかりやすく伝える資産」となり、長期的に費用対効果を生み出します。
費用対効果を見誤る3つのポイント
経営者がデザイン投資を判断する際、見誤りやすいポイントがあります。
・短期的な売上だけで判断してしまう
・制作費用を「支出」とだけ見てしまう
・成果を測定する仕組みを持たない
デザインは広告のように即日で成果が出るものではありません。
それを「すぐに売上に反映されないから無駄だ」と考えてしまうと、本来の価値を見逃してしまいます。
経営的に見るべきは「どれだけ長期にわたり利益をもたらす資産になるか」という視点なのです。
デザイン投資がもたらす経営効果
では、具体的にデザイン投資はどのような経営効果をもたらすのでしょうか。大きく分けると次のようなポイントがあります。
・顧客獲得コストを下げる
・リピート率や顧客ロイヤルティを高める
・採用活動における信頼性を向上させる
・価格競争に巻き込まれにくくなる
たとえば、見込み客が競合と比較する際、デザインが洗練されているだけで「信頼できそう」「ちゃんとしている会社」という評価につながります。
その結果、商談率や成約率が上がり、広告費を削減できる可能性もあります。
数値化しにくい効果をどう評価するか
経営において重要なのは、成果をいかに測定するかです。
デザインの効果は数値化が難しいと言われますが、次のような観点から評価することが可能です。
・問い合わせ数や成約率の変化
・リピート購入率や来店頻度の推移
・ブランド認知度やSNSでの反応
・採用エントリー数の増減
直接的な売上だけではなく、顧客や市場の行動変化を観測することで「デザイン投資のROI(投資対効果)」を把握できます。
成功する企業が重視する「一貫性」
成功している企業ほど、デザインを単発の施策ではなく「統一された戦略の一部」として活用しています。
チラシ・ホームページ・SNS・パンフレットなど、顧客と接するあらゆる場面で一貫性を持たせることで、認知や信頼を積み重ねています。
一度整えたデザイン資産は、広告・営業活動・採用・店舗運営など幅広い領域で効果を発揮し続けます。
これは「長期にわたって利益を生み出す資産」としての費用対効果の高さを示しています。
デザイン投資を経営判断するための視点
経営者がデザイン投資を判断する際には、次のような視点を持つことが重要です。
・短期的な費用ではなく、中長期的な収益にどう貢献するか
・競合との差別化をどれだけ明確にできるか
・社員や顧客に「自社の強み」を伝える武器になるか
デザイン投資を「費用」と考えるか「資産」と捉えるかで、企業の成長スピードは大きく変わります。
経営判断においては、見えやすいコストだけではなく「将来的に得られる価値」に注目する必要があります。
まとめ
デザイン投資は「すぐに結果が出るものではない」という側面があるため、費用対効果を軽視されがちです。
しかし、経営の視点で見れば、デザインは信頼を高め、競争力を強化し、長期的に利益を生む大切な資産です。
「デザインにどれだけ投資するか」ではなく「投資をどう活かすか」という視点を持つことが、これからの企業にとって不可欠です。

私たちアメージングデザインでは、戦略設計から関わり、企業の強みを「成果につながるデザイン」として形にするお手伝いをしています。
「コストではなく資産となるデザイン」を一緒に育てたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。
「結果に直結するデザイン」を、経営の視点から一緒に考えてみませんか?