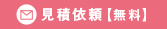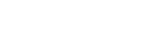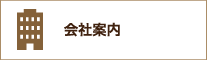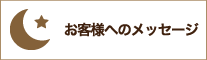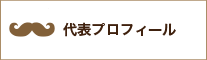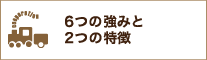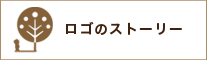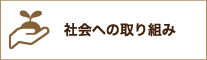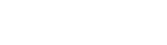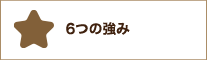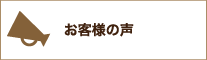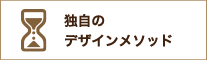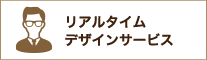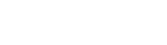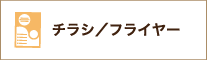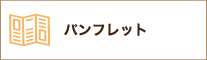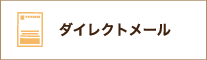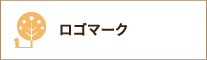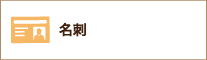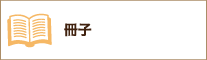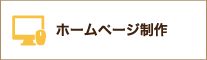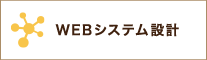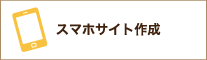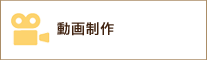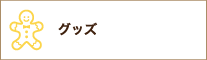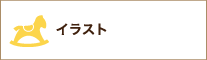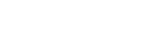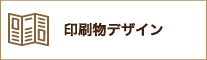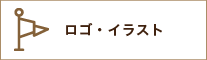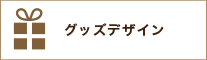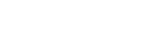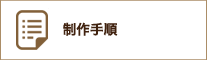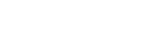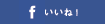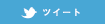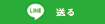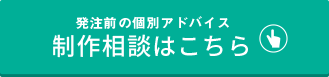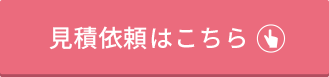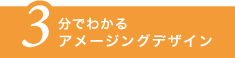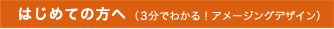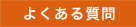TOPICS
デザインやWEBの反応を成果に変える検証の仕組み
「一度作ったけど、反応がいまいちだった」
「どこを直したら良くなるのか、感覚でしか判断できない…」
こうした課題は、チラシやWEBなど販促ツールを使う多くの事業者に共通しています。
制作後に“振り返り”を行っていない、あるいは“記録しても次に活かせていない”ことで、改善のチャンスを逃しているのです。
この記事では、成果に直結する『振り返り設計』の考え方と、その実践ステップをお伝えします。

目次
1. 振り返りは「制作後の後始末」ではなく「次回のための設計」
まず前提として押さえておきたいのは、振り返りは“反省”ではなく“戦略”だということ。
作って終わりにするのではなく、その成果とプロセスを次に活かせる「記録と設計」が、振り返りの本来の目的です。
・何が良かったか
・何が機能しなかったか
・どこに改善余地があるか
この3点を明文化することで、次回制作の精度とスピードは大きく向上します。
2. 「数値」と「主観」を分けて記録する
振り返りで陥りやすいのは、「なんとなくよかった/悪かった」と曖昧な主観だけで評価してしまうことです。
これでは再現も改善もできません。
そこで、以下のように「数値」と「印象」を分けて整理しましょう。
■ 数値(できるだけ定量化)
・配布数、閲覧数、反応数、成約数など
・反応率(例:アクセス数に対する問い合わせ率)
・SNSや広告のクリック率など
■ 印象・感覚(定性的評価)
・問い合わせ内容の傾向
・お客様の反応(驚き、好印象、誤解など)
・配布時の感触(受け取りやすさ、反応のリアル)
この2つを別々に記録することで、分析の精度が高まり、次の一手が明確になります。
3. 改善の「着眼点」を整理しておく
振り返りの効果を高めるためには、毎回見るべき“着眼点”をあらかじめ設けておくのが有効です。
以下は代表的な振り返りポイントです。
・ターゲットに届いていたか?
・メインコピーは刺さったか?
・情報量は適切だったか?
・視線誘導やレイアウトに問題はなかったか?
・問い合わせボタンやフォームは見つけやすかったか?
このように“チェックリスト化”することで、同じ視点で継続的に改善ができ、属人化も防げます。
まとめ
販促物は「作って終わり」ではなく、「次にどう活かすか」が成功の分かれ道です。
とくにチラシやWEBサイトなどの施策は、一度で完成するものではなく、仮説と検証を繰り返すプロセスです。
振り返り設計を仕組み化することで、以下のような状態が実現します。
・次回制作の方向性に迷わない
・制作チーム間での共有がスムーズになる
・数字で成果を語れるようになり、上司や関係者にも納得感を得られる
・根拠ある改善ができるので、成果も伸びやすくなる
つまり、“振り返りの質”が“次の成果の質”を決めるのです。
私たちアメージングデザインでは、“目的を達成するため”のデザインを、
お客様一人ひとりの目的を丁寧におうかがいし、それに合わせたプランニングから開始いたします。
プランニングとは、「他社との違い」「独自のポジション」「明確な顧客像」を基に、「誰に」「何を」「どのように伝えるか」を設計することです。
そこから訴求する情報を整理して、紙面でどのように見せていくかを検討します。
これらが、しっかりできてはじめてデザイン制作に入ります。

このプロセスをすることで、私たちアメージングデザインは、2010年の創業以来、営業やセールスを一切せずデザイン戦略のみでの自社集客を実現することができました。
もちろん弊社のお客様もそのような方が多くいらっしゃいます。
詳しくはお客様の声をご覧ください。
これからはじめて販促物を作成されるお客様にも、分かりやすくサポートいたします。