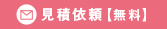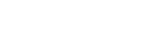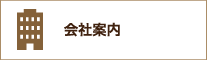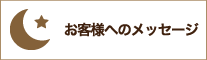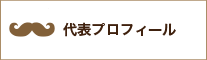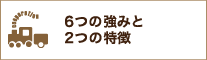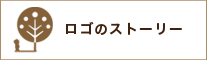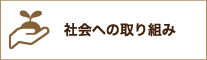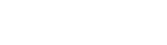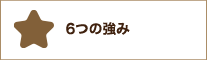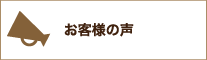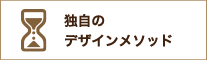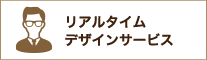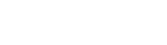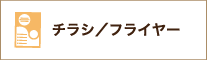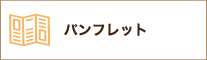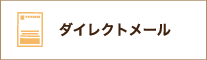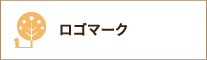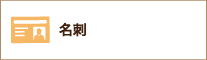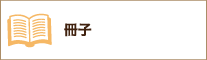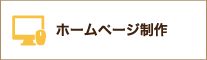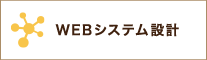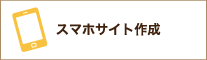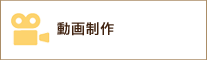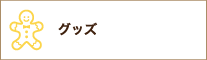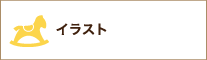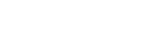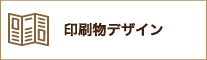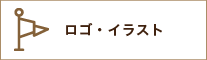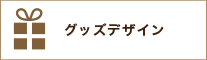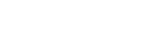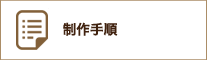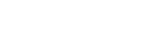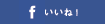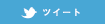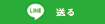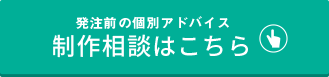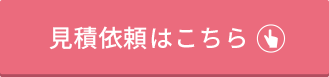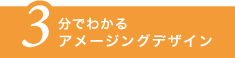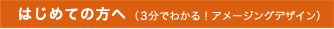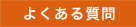TOPICS
販促物の改善はここから!反応データの見かたと活かし方入門
「チラシを配っても反応が薄い」
「LPをリニューアルしたのに、成果につながらない」
そんな状況に直面したとき、見直すべきは「感覚」ではなく「データ」です。
販促物の改善には、ユーザーの反応を客観的に分析し、その結果を次に活かすことが不可欠です。
この記事では、販促物の改善に活用できる反応データの種類と、実際の改善にどう結びつけるかを、マーケティングとデザインの視点からご紹介します。

目次
1. 「なんとなく良さそう」で終わらせない
販促物を作るとき、「見た目がキレイ」「デザインが気に入っている」という判断だけで完結していませんか?
本来の目的は「成果につなげること」です。
そのためには、配布後・公開後の反応を「計測」することが重要になります。
反応の手がかりは、数値や行動データの中にこそあります。
2. 反応データにはどんな種類がある?
販促物ごとに取得できるデータは異なりますが、以下のような指標を参考にできます。
・Web:アクセス数/クリック率/直帰率/コンバージョン率
・チラシやDM:QRコードやキャンペーンコードの使用数、電話・問い合わせ件数
・店舗販促:来店数の変化/アンケート回答/配布したチラシの持ち込み数
これらを記録・比較することで、改善のヒントが得られます。
3. 「どこで離脱しているか」を見極める
デザインや構成を改善するには、「どの時点でユーザーの関心が離れているか」を把握することが大切です。
たとえばLPであれば
・ファーストビューで離脱している → メインビジュアルやキャッチコピーに問題あり
・詳細説明まで読まれているがCVしない → メリットの訴求が弱い、CTAが不十分
チラシであれば
・裏面まで見られていない → 情報量やレイアウトが適切かを再考
こうした判断材料として、ヒートマップやアクセス解析ツールが有効です。
4. 改善につなげるための視点とは
データを見ても、ただ数値だけを眺めて終わってしまうことがあります。
重要なのは、そこから「なぜこの数値なのか?」という仮説を立てることです。
・ターゲットに伝わる言葉になっているか
・見せ方やレイアウトは読みやすいか
・お得感・信頼感は伝わっているか
こうした視点で「改善すべき要素」を見つけ出すことが、デザインの成果を上げる鍵になります。
5. データと感覚をバランスよく活かす
数値だけを追いすぎると、デザインが無機質になることもあります。
一方で、感覚だけに頼ると改善の軸がぶれてしまいます。
・数字が示す事実を冷静に読み取る
・ユーザー目線の感覚をデザインに落とし込む
この2つをバランスよく取り入れることで、「成果につながる販促物」に仕上がっていきます。
まとめ
販促物は作って終わりではなく、「結果から学んで育てていく」ものです。
そのためには、定期的に反応データを見返し、改善を繰り返すことが不可欠です。
私たちアメージングデザインでは、成果を重視したデザイン設計と、検証・改善を前提とした制作支援を行っています。

「なんとなく作る」から、「根拠ある改善」へ。
成果を出す販促ツールをご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
販促物の改善に欠かせない「反応データの見かたと活かし方」をマーケティング視点で解説。チラシ・LP・DMなどの効果を高めたい方に向けた実践ガイドです。