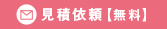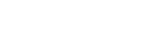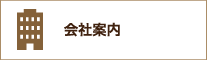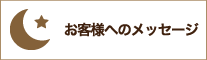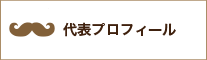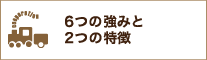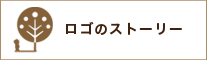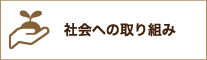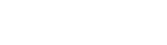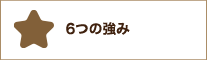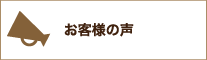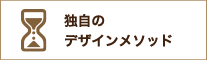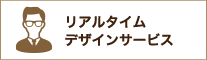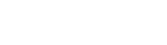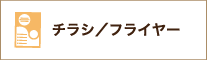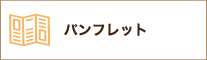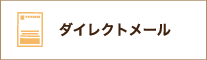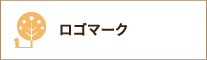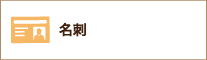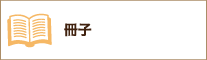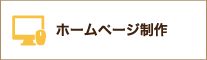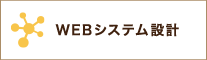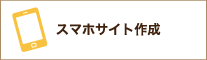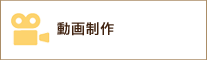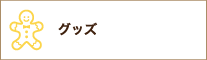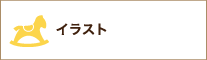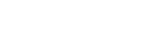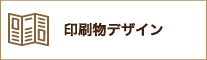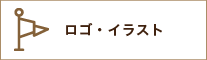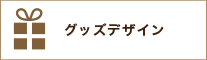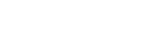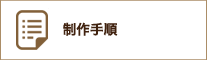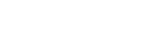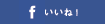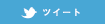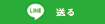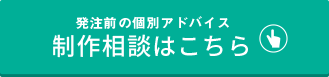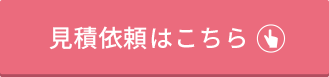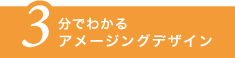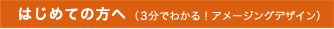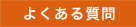TOPICS
「伝えたいことが多すぎる」企業ほどデザインで失敗するワケ

目次
「全部伝えたい」は間違い?情報過多がもたらす逆効果
企業として伝えたいことが多いのは当然です。
サービスの強み、創業の想い、商品ラインナップ、導入事例、価格の柔軟性…できればすべてを見込み客に伝えたいと考えるのは、経営者や広報担当者の自然な心理でしょう。
しかし現実には、『伝えたいことを全部詰め込んだ結果、何も伝わらなくなる』という失敗に陥る企業が少なくありません。
特にパンフレットやWebサイト、LPといった「第一印象を決める媒体」では、情報過多は致命的です。
見る側が“迷う・疲れる・興味を失う”という状態に陥り、反応率が大きく下がってしまいます。
なぜ情報量が多いほど「わかりにくく」なるのか
「わかりやすさ」は、情報の『量』ではなく『構造』で決まります。
しかし実際の現場では、多くの企業が次のような状態に陥っています:
- あれもこれも掲載した結果、フォントサイズが小さくなり読みにくい
- 要素が多すぎて視線が散らばり、重要な情報が埋もれてしまう
- 何を見て欲しいのか、どこから読めばいいのかわからない
これでは、お客様が自分に関係のある情報を素早く見つけられず、せっかくの訴求ポイントもスルーされてしまいます。
特に中小企業の販促物では、『伝えすぎて伝わらない』というパターンが非常に多く見られます。
重要なのは「削る」ことではなく「選ぶ」こと
誤解されがちですが、「情報を削る」のが目的ではありません。
本当に必要なのは、『何を最も伝えるべきか』を選び抜くことです。
企業が本当に届けたい価値は何なのか。
見る人が最初に知りたい情報は何なのか。
判断のポイントとなる要素はどこにあるのか。
これらを整理し、優先順位をつけることが、デザインの第一歩です。
伝えたい情報すべてを“掲載”することは可能ですが、“同じ重み”で伝えるのは不可能。
だからこそ、『軸を決めて、それを中心に設計する』という構造が必要になるのです。
情報整理の成功事例:視点を絞るだけで問い合わせ数が増加
ある製造業の企業では、自社技術の強みや多様な対応力を前面に出した複数ページのパンフレットを配布していましたが、反応は芳しくありませんでした。
当社でヒアリングを行い、「1番強い商材×1番成果が出ている事例」を軸にした構成へリニューアル。
他のサービスはあえて裏面にまとめ、『まずはこれ』を明示した結果、問い合わせ率は以前より向上しました。
伝えたい気持ちを一度リセットし、見る人の「入り口の視点」に立って再構成することで、情報の受け取りやすさが格段に変わったのです。
まとめ:デザイン設計とは、伝える順番を整えること
デザインは単なる装飾ではありません。
『伝える情報を選び、順番を整え、受け手の理解を助ける仕組み』です。
企業としての想いが強いほど、情報は増えていきます。
しかし、それをすべて一度に見せようとすると、本当に届けたいメッセージが霞んでしまう。
だからこそ、最初に『伝えるべき価値』を定め、その軸に沿った情報設計が重要なのです。
私たちアメージングデザインでは、ビジネスの本質とゴールに立ち返りながら、見込み客に伝わる情報設計とデザインの支援を行っています。

「うちは情報が多すぎるかもしれない」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。