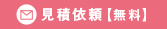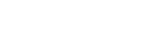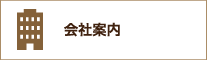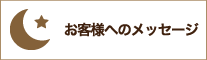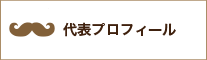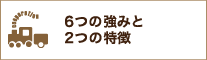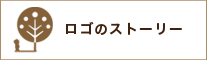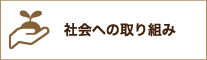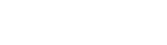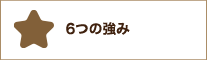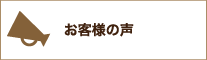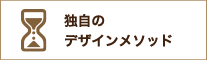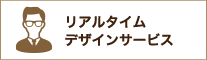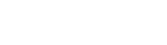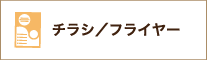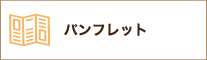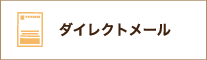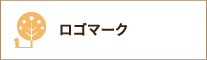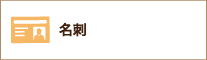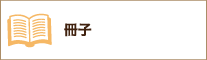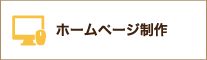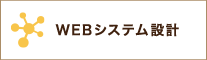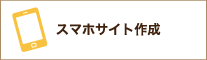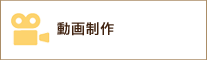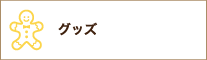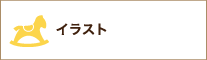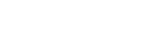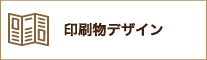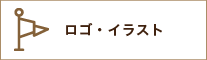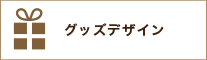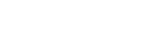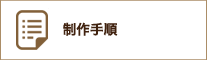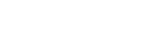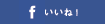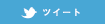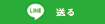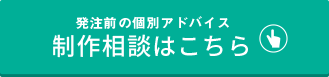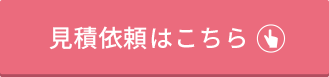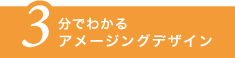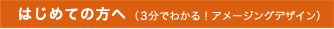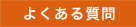TOPICS
成果につなげるデザイン構成の考え方とは
デザインのクオリティが高くても、なぜか反応がない。
その原因は『構成設計』にあるかもしれません。
構成とは、情報をどの順番で、どのように配置するかという“伝え方の設計図”。
読まれる順番、理解される順番、そして心が動く順番に意味を持たせることが、デザイン成果を最大化する鍵になります。
この記事では、「なぜその順番で情報を並べるのか?」という視点から、構成設計の基本と実践について解説します。

「読み手の流れ」で構成を考える
構成設計で最初に意識すべきは、送り手の都合ではなく『読み手の流れ』です。
・誰が
・どんな状況で
・どのくらいの時間をかけて読むのか
これらを想定すると、次のような順番で情報を設計すべき理由が見えてきます。
・最初に目を引くキャッチコピーで「読む価値」を伝える
・次に具体的な課題提示や共感で「引き込む」
・そこから解決策や実績で「納得」させる
・最後に行動導線(申込・問合せ)で「動いてもらう」
この流れは、LPでもチラシでもパンフレットでも共通する、成果につながる構成の基本です。
構成に必要な3つの視点
構成設計をする際、次の3つの視点を持つことが重要です。
・ゴールから逆算する(最終的に何をしてもらいたいか)
・ターゲットの理解度にあわせる(前提知識・関心レベル)
・読まれる順番と視線の動きを設計する(視覚設計と連動)
このように、「ただ情報を載せる」のではなく、「どんな順番なら伝わるか」を軸に設計することで、同じ内容でも印象や成果が大きく変わります。
成果を出す構成に共通するポイント
成果につながる構成には、いくつかの共通点があります。
・一番伝えたいことは“最初に、強く”伝える
・文字だけでなく図やビジュアルも組み合わせて視覚的に整理する
・不要な情報は削り、優先順位をつけて配列する
・ひとつの流れの中で「共感 → 解決 → 行動」へと誘導する
特に、情報過多になりがちなパンフレットなどでは、構成に「目的からの取捨選択」が求められます。
まとめ
構成設計とは、ただ情報を並べることではなく、「伝わる順番」を設計することです。
読む人の視点で流れを設計し、目的から逆算して取捨選択することで、成果に繋がるデザインが生まれます。
私たちアメージングデザインでは、“目的を達成するため”の構成設計を、
お客様一人ひとりの目的を丁寧におうかがいし、それに合わせたプランニングから開始いたします。
プランニングとは、「他社との違い」「独自のポジション」「明確な顧客像」を基に、「誰に」「何を」「どのように伝えるか」を設計することです。
そこから訴求する情報を整理して、紙面でどのように見せていくかを検討します。
これらが、しっかりできてはじめてデザイン制作に入ります。

このプロセスをすることで、私たちアメージングデザインは、2010年の創業以来、営業やセールスを一切せずデザイン戦略のみでの自社集客を実現することができました。
もちろん弊社のお客様もそのような方が多くいらっしゃいます。
詳しくはお客様の声をご覧ください。
これからはじめて販促物を作成されるお客様にも、分かりやすくサポートいたします。