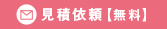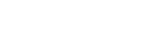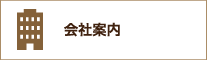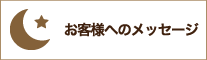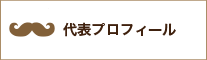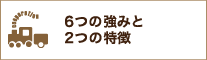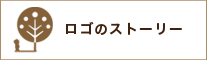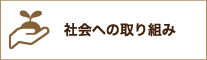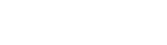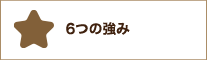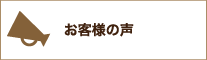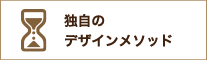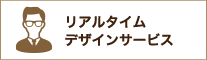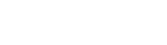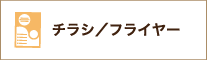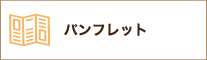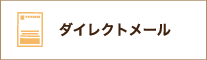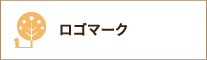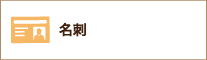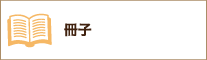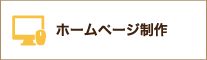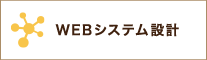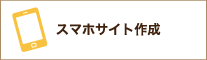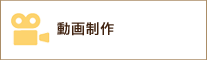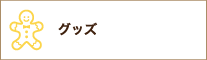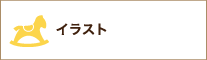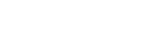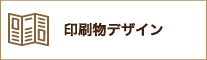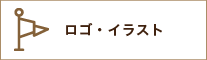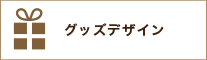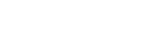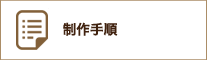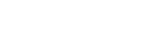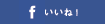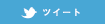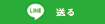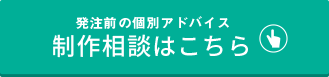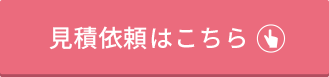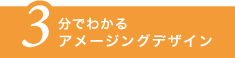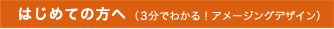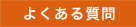TOPICS
デザイン会社に依頼するときによくある失敗例とその回避法
「デザイン会社に依頼したけれど、出来上がったものが思っていたイメージと違った」
「時間もコストもかけたのに、成果につながらなかった」
実際にこのような経験をした企業は少なくありません。
デザイン制作は決して安い投資ではないため、失敗してしまうと社内の信頼や予算にも大きな影響を与えてしまいます。
ですが、多くの失敗は避けられるものです。
なぜなら、その原因の多くは『準備不足』や『認識のすれ違い』にあるからです。
依頼側が少し意識を変えたり、進め方を工夫したりするだけで、成果を大きく改善できるのです。
この記事では、デザイン会社に依頼するときによくある失敗例を整理し、それをどう防げばよいのか、実践的な回避法とともにご紹介します。

目次
1. 目的が曖昧なまま依頼してしまう
最も多い失敗例のひとつが「目的を明確にしないまま依頼してしまう」ことです。
例えば「とにかく新しいパンフレットが欲しい」という依頼では、どんなデザインが成果につながるのか判断できません。
結果として、『かっこよさはあるけれど、成果につながらないデザイン』が出来上がり、印刷や公開後に「効果がなかった」と後悔するケースにつながります。
【回避法】
依頼前に「このデザインで何を達成したいのか」を整理しましょう。
新規顧客を獲得したいのか、既存顧客をフォローしたいのか、ブランドイメージを高めたいのか。
目的を明確にすることで、デザイン会社も最適な提案ができるようになります。
2. ターゲットを決めずに「みんなに響くもの」を求める
「できるだけ多くの人に響くデザインをお願いします」——このような依頼もよくあります。
一見すると合理的に思えますが、結果的には誰にも強く刺さらないデザインになることが多いのです。
例えば、若年層と経営層を同時に狙った場合、両方の特徴を中途半端に取り入れることになり、伝わりにくい仕上がりになるリスクが高まります。
【回避法】
「このデザインは誰に届けたいのか」を決めましょう。
年齢層、職業、ライフスタイル、抱えている悩みなどを具体的に絞り込むことで、デザインは一気に伝わりやすくなります。
3. 情報や素材が不足している
「とりあえずお願いしたいので、細かい情報はお任せします」というスタンスも失敗の原因になりがちです。
デザイン会社は魔法使いではありません。素材や情報が不足していれば、どれだけ工夫しても「中身が薄いデザイン」になってしまいます。
例えば、商品写真が用意されていなければイメージ写真を使うしかなく、オリジナリティや説得力に欠ける結果になります。
【回避法】
依頼前に「会社紹介文」「商品・サービス情報」「ロゴデータ」「過去の資料」などを整理しておきましょう。
必要に応じて写真撮影や文章のブラッシュアップを事前に進めると、完成度が格段に高まります。
4. イメージ共有が不十分でズレが生じる
「シンプルにしてほしい」「おしゃれにしてほしい」といった言葉は、人によって受け取り方が大きく異なります。
依頼者が思う「シンプル」と、デザイン会社が捉える「シンプル」が違えば、出来上がった成果物に大きなズレが生まれます。
【回避法】
参考資料を用意するのが一番効果的です。
「このサイトの雰囲気が近い」「このパンフレットのレイアウトが好み」といった具体例を見せることで、言葉では伝えきれないイメージを共有できます。
5. スケジュールや予算を曖昧にしたまま進める
「できるだけ早く、安く」という依頼はよくありますが、無理な条件で進めると質が犠牲になりやすいのが現実です。
さらに、スケジュールや予算が曖昧なまま進めてしまうと、途中で「思ったより費用がかかる」「予定より完成が遅れる」といったトラブルにつながります。
【回避法】
大まかで構いませんので、予算の上限や納期の希望を事前に整理しましょう。
余裕を持ったスケジュールを設定することで、デザイン会社も提案の幅を広げることができ、結果的により良い成果を得られます。
まとめ
デザイン会社に依頼する際の失敗は、「目的が曖昧」「ターゲット不在」「素材不足」「イメージのすれ違い」「予算やスケジュールの不明確さ」といった共通点があります。
これらはすべて、事前の準備やコミュニケーションで防ぐことができます。
依頼側が「何を求め、誰に届けたいのか」を整理し、具体的に共有することで、デザイン会社は本来の力を発揮できます。
その結果、見た目が美しいだけでなく『成果につながるデザイン』が生まれるのです。
私たちアメージングデザインでは、戦略設計から参加し、企業やサービスの強みを「伝わるカタチ」にするサポートを行っています。
見た目だけでなく、「伝わるための仕組み」としてのデザインが必要な方は、ぜひご相談ください。

「結果に直結するデザイン」を、プロジェクトの初期から一緒に考えてみませんか?