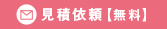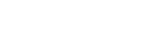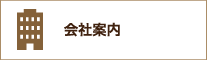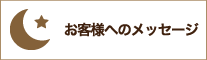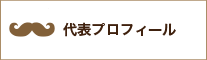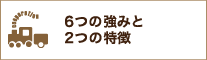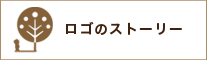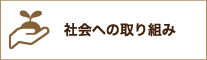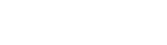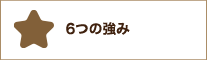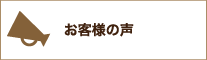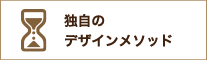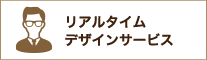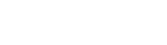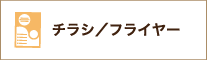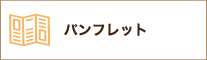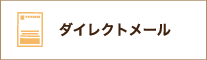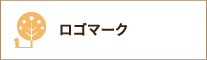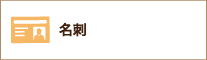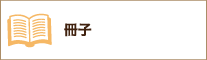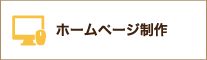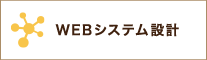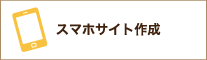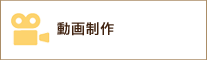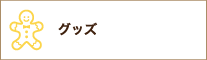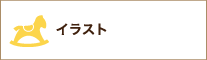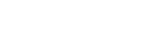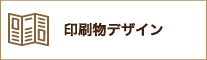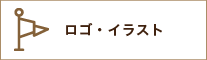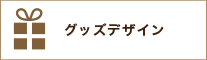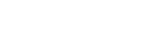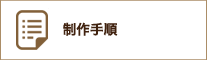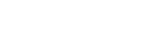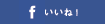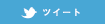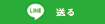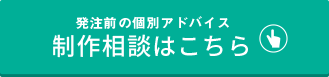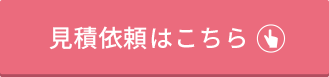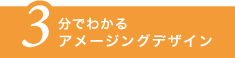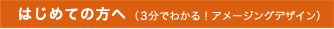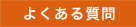TOPICS
パンフレット設計で見落とされがちな5つのポイントと対策
パンフレットは、自社の魅力やサービス内容を伝える重要なツールです。
にもかかわらず「なんとなく構成した」「掲載したい情報を詰め込んだだけ」という理由で、反応が取れないパンフレットになってしまっているケースは少なくありません。
本記事では、見落とされがちな設計ポイントとその対策を、デザイン戦略の視点から解説していきます。

1. 情報が“並列”になっている
多くのパンフレットで見受けられるのが、「情報を並べただけ」の構成です。
これは読み手にとって、どれが重要なのか判断できず、印象にも残りません。
【対策】
・内容に優先順位をつける
・読み手の関心に合わせて情報をグルーピングする
・ストーリー性をもたせる(例:課題提示 → 解決策 → 実績 → アクション)
構成設計は、情報の“順番”を考えるところから始まります。
2. ターゲット像が曖昧
すべての人に好かれるように、あれもこれも…と詰め込んだ結果、誰の心にも刺さらないパンフレットに。
これは設計段階で「誰に読ませるか」が決まっていない証拠です。
【対策】
・メインターゲットを明確にする(年齢層/役職/悩みなど)
・その人が知りたい情報に絞って伝える
・読み手の視点から「どんなメリットがあるか」を表現する
「誰向けか」がはっきりしていると、デザインやコピーもブレなくなります。
3. 文字サイズと余白の設計不足
読みづらいパンフレットは、内容以前に「読む気」が削がれます。
その原因の多くは、文字が小さすぎること、そして余白が足りないことにあります。
【対策】
・本文サイズは10pt以上を目安に
・見出しと本文に十分な視覚的差をつける
・段落やセクションごとに余白をとる
・箇条書きを使い、情報のブロック化をする
「見やすさ」はそれ自体が信頼感をつくる要素です。
4. CTA(次の行動)導線が弱い
読み終わったあと「で、どうすればいいの?」という状態になっていませんか?
せっかく興味を持ってもらっても、次の行動が示されていなければ、成果にはつながりません。
【対策】
・「今すぐ無料相談」「来場予約はこちら」などのアクションを明記
・連絡手段は複数掲載(電話・QR・WEB)
・CTAボタンやエリアは目立たせる
・パンフレットの末尾でしっかり導く構成にする
CTAは「伝えっぱなし」で終わらせないための必須パーツです。
5. 配布シーンを想定していない
どのような状況で、誰がこのパンフレットを手にするか。
これを想定していないと、サイズや構成、言葉遣いが的外れになってしまうことも。
【対策】
・対面配布/設置型/郵送など配布方法を決めてから設計する
・使用シーンに応じて、簡潔にすべきか/詳しく説明すべきかを判断する
・持ち帰ってもらいやすい仕様(サイズ、紙質、折りなど)を選ぶ
「設計」とは、デザインそのものだけでなく、使用状況やユーザー体験を前提に考えることでもあります。
まとめ
パンフレットで成果を上げるには、見た目だけでなく「設計の意図」が必要です。
今回紹介した見落とされがちな5つのポイントを、あらためて振り返ってみましょう。
・情報の優先順位とストーリー性があるか
・ターゲットが明確に想定されているか
・読みやすさ(文字と余白)は配慮されているか
・行動導線(CTA)がしっかり設計されているか
・使われるシーンを前提に構成されているか
これらを踏まえることで、「読む人が迷わない・動きたくなる」パンフレットへと近づきます。
私たちアメージングデザインでは、“目的を達成するため”のデザインを、
お客様一人ひとりの目的を丁寧におうかがいし、それに合わせたプランニングから開始いたします。
プランニングとは、「他社との違い」「独自のポジション」「明確な顧客像」を基に、「誰に」「何を」「どのように伝えるか」を設計することです。
そこから訴求する情報を整理して、紙面でどのように見せていくかを検討します。
これらが、しっかりできてはじめてデザイン制作に入ります。

このプロセスをすることで、私たちアメージングデザインは、2010年の創業以来、営業やセールスを一切せずデザイン戦略のみでの自社集客を実現することができました。
もちろん弊社のお客様もそのような方が多くいらっしゃいます。
詳しくはお客様の声をご覧ください。
これからはじめて販促物を作成されるお客様にも、分かりやすくサポートいたします。